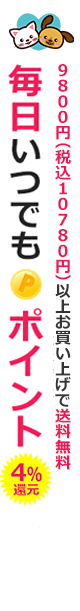| サイトが気に入ったら押してもらえると嬉しいです ⇒ ツイート |


犬グループと猫グループの戦い!?
犬猫グループは寒さ自体というよりは、寒冷化が豊かな森に大きな変化を起こします。 いままでの居住地の森に住み続けることができたのが 猫グループです。 犬グループは森という住み慣れたテリトリーを追われ、平原での適応を迫られたと考えられます。 実際に、同じ大きさのネコ科動物とイヌであれば、圧倒的にネコ科動物が戦いに勝ちます。ネコ科動物は、口だけでなく、両手の爪、柔軟な身のこなしで、イヌの戦闘能力をはるかにしのぎます。 一方、イヌ科動物は、平原の長距離移動に適した身体に進化しています。手足は、狩りに適した構造から 歩行移動に適した構造に変化しています。 これは、不思議なことに、森に住んでいたサルが、気候変動で森がなくなり、平原に住むことになった人間の進化の方向と同じ です。人の場合は、それが700~400万年前に起こり、平原での移動でエネルギー効率の良い骨格構造へ変化したと(それが直立2足歩行)考えられています。 犬は、平原を移動することに適した手としたため、手の武器(器用さ)を失いました。人は、同様に平原を移動することに適した足としたため、足の器用さを失いました(サルの後ろ足は枝をつかむことができます)。 時代の違い、手と足という違いはありますが、犬と人は、過去の歴史に、似たような環境変化にさらされ、似たような適応と、思考を身に付けた可能性があるのです。 犬と人との、不思議な縁 を感じます。 いまでも、猫科動物が、獲物の豊富な熱帯地方(太陽光が豊かで植物が繁茂し、その植物を食べる動物が豊か)にライオン、トラなどとして生息しています。 そして、イヌ科動物の代表のオオカミは、太陽光が少なく食料となる動物が限られた寒い北方地方でオオカミが暮らしています。この図式は、いまでも当てはまる気がします。 |
オオカミはなにを食べているのか?
鹿はいろいろな種類がいます。 これに、牛科(ヨーロッパバイソンなど)や、マウンテンシープなどを加えると、地域差はありますが、鹿、牛、羊、ヤギなど野生の反芻草食動物でおよそ7~8割以上の食事を確保していると報告されています。 鹿が多く取れる地域は、鹿を特に好んで狩りをしており、鹿だけで75%以上のの食事比率になっているようです。 (ゼッケンバーグ研究所の調査が有名なようです。8年間で3000以上のオオカミの糞を採取分析し、食性を逆算して調査したものです。ここでは96%以上が鹿など有蹄類であった) 残りの食べ物は、地域により獲物の種類やその生息数が変わるため内容が変わりますが、2~3割ぐらいを、マーモットなどのジリス、ウサギ、ネズミ、キツネなどを食べていると報告されています。 重要なことは、鹿を食べているということですが、さらに、掘り下げると、オオカミは、鹿類、牛類、羊類などの4つの胃を持つ反芻動物ばかりを選んで食べているという事実です。 |
| 6500万年前の食肉動物が犬の祖先(犬の進化①) | |
| 犬猫グループは肉食動物の中の肉食動物(犬の進化②) | |
| 犬グループと猫グループの戦い!?(犬の進化③) | |
| 鹿に隠された秘密(犬の進化④) | |
| 広大な草原の出現(犬の進化⑤) | |
| イネ科を消化できる反芻動物(犬の進化⑥) | |
| 犬に玉ネギが悪い理由(犬の進化⑦) |

| サイトが気に入ったら押してもらえると嬉しいです ⇒ ツイート |
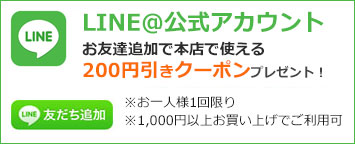 |  |

|
 |
TOP > コラム一覧 >犬グループと猫グループの戦い!?(犬の進化③)





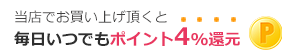
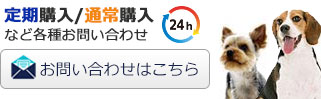







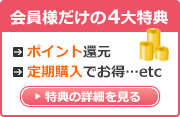



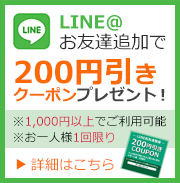

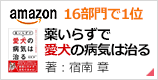

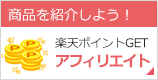

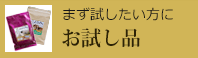
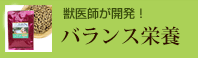
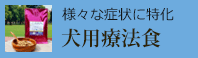
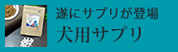
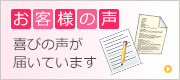

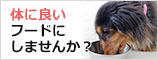


 地上で最強の肉食動物になった犬猫グループ(食肉類)ですが、彼らに地球寒冷化が襲います。
地上で最強の肉食動物になった犬猫グループ(食肉類)ですが、彼らに地球寒冷化が襲います。 進化の過程をちょっと飛ばして、犬はオオカミを先祖としています。
進化の過程をちょっと飛ばして、犬はオオカミを先祖としています。